「子どもと笑顔で過ごしたい」──その願い、私も毎日のように胸の中でそっとつぶやいています。
でも現実は、思うようにいかないことばかり。
寝かしつけが長引いたり、家事と育児が重なったり…気づけばイライラして、あとで落ち込んでしまう。そんな日、ありますよね。
大丈夫です。
その気持ち、痛いほどわかります。
私も保育士としてたくさんの親子を見てきましたが、いま二児の母になって実感しているのは、
「どんなに愛していても、心が追いつかない日がある」という当たり前の事実です。
それでもあなたは毎日、子どものことを思って動いていて。
眠い目をこすりながら抱っこしたり、泣き声に向き合ったり…その全部が、すでに十分すぎるほど“頑張っている証拠”なんです。
だからこそ今だけは、ほんの少しだけ立ち止まって、
“自分を責めない子育て”をいっしょに始めてみませんか?
この記事では、心理学や保育の知識だけでなく、
私自身が「つらかった日」から抜け出すために実際に試してきた
10の考え方と、小さな心の工夫をお届けします。
読み終えるころには、きっと胸の奥がふっと軽くなって、
「よし、もう一度笑ってみよう」
そんなやさしい気持ちが、あなたの中に静かに戻ってきます。
- 1. 「完璧な親」になろうとしない|“できない日”があっても大丈夫
- 2. 子どもの「できた!」を一緒に喜ぶ|小さな成長を見逃さない
- 3. 「ひとり時間」を罪悪感なしでつくる|ママ・パパの笑顔が子の安心に
- 4. イライラを感じたら「深呼吸3回」|感情をリセットする小さな習慣
- 5. 「ありがとう」を増やすと、家庭がやわらかくなる
- 6. 比べない子育て|他の家庭と違っていい
- 7. 子どもを信じる力を育てる|“見守る勇気”を持つ
- 8. 「助けて」を言える親になる|頑張りすぎない勇気
- 9. 日常に“楽しい仕掛け”をつくる|笑いと遊びが育児を変える
- 10. 今日の自分をほめて終わる|「よくやってるよ」と言える夜に
- まとめ|完璧じゃなくていい、“笑顔でいる時間”を少しずつ増やそう
1. 「完璧な親」になろうとしない|“できない日”があっても大丈夫
「もっとちゃんとしなきゃ」「他のママみたいにできない」──私も、そう思って泣いた夜が何度もあります。
離乳食を手作りできなかった日も、洗濯物が山のように積まれた日も、「私って母親失格かも」と心の中で責めていました。
でも、ある日、子どもが私の顔をのぞきこんで「ママ、だいすき」って言ったんです。
部屋は散らかっていたけれど、その笑顔を見た瞬間、「この子は“完璧なママ”じゃなくて、“安心できるママ”を求めてるんだ」って気づきました。
それからは、できない日があっても「まぁ、いっか」と笑えるようになりました。
完璧じゃなくても、抱きしめるたびに愛はちゃんと伝わっています。
「今日もがんばった自分に、“よくやってるよ”って言ってあげよう。」
2. 子どもの「できた!」を一緒に喜ぶ|小さな成長を見逃さない
子育てって、気づくと「もっとできるように」「早くできてほしい」と思ってしまうものですよね。
私も長男が2歳のころ、周りの子と比べて「まだオムツが外れない」「言葉が遅い」と焦ってばかりいました。
でも、ある日ふとした瞬間に、「ママ、みて!できた!」と積み木を3つ重ねた彼の顔を見て、ハッとしたんです。
私、ちゃんと“できた瞬間”を見てあげていなかったなって。
その日から、どんな小さなことでも「できたね!」って一緒に喜ぶようにしました。
不思議とその頃から、子どもの笑顔が増え、私の心も穏やかになっていきました。
「すごいね」「がんばったね」という言葉は、子どもの心に“自信のタネ”を植える魔法なんです。
「できたね」を重ねるたび、親子の笑顔も増えていく。──その瞬間を、どうか見逃さないで。」
3. 「ひとり時間」を罪悪感なしでつくる|ママ・パパの笑顔が子の安心に
子どもを預けてカフェに行くだけで、「こんなことしていいのかな」と胸がチクッとした日がありました。
周りのママは頑張っているのに、私だけ休むなんて…って、自分を責めてしまったんです。
でも、ある日、ワンオペでクタクタになった夜、息子が私の顔を見て言いました。
「ママ、にこにこじゃないね。」
その言葉が胸に刺さりました。
ああ、私の笑顔が減っていることに、この子はちゃんと気づいていたんだ──そう思った瞬間、涙が止まりませんでした。
それから少しずつ、「ひとりの時間を持つことは、この子のためにも必要なんだ」と考えるようになりました。
10分だけ好きな音楽を聴く、温かいお茶をゆっくり飲む、それだけでも心がやわらぎます。
親の笑顔は、子どもにとっての安心のサイン。
どうか、自分を休ませることに、もう罪悪感を持たないでください。
「ひとりで息を整える時間が、家族の笑顔を守ってくれる。」
4. イライラを感じたら「深呼吸3回」|感情をリセットする小さな習慣
正直に言うと、私はよくイライラしていました。
特にワンオペの日。ごはんを作っているそばから「ママー!」「こぼれたー!」の声。
心の中で「もう、どうして私ばっかり…」とつぶやいた瞬間、涙が出そうになることもありました。
ある夜、怒鳴ったあとに眠る子どもの寝顔を見て、胸がぎゅっと痛くなりました。
「ごめんね…本当は、優しくしたいのに。」
そんなとき、保育士時代の先輩から教えてもらった言葉を思い出したんです。
“イライラしたら、まずは深呼吸を3回してみて。”
それ以来、怒りの波がきたときは「吸って、吐いて」を3回。
それだけで、ほんの少し気持ちが落ち着くようになりました。
深呼吸は、自分の心を守る小さな魔法。
そしてその静けさは、子どもにもやさしく伝わっていきます。
「息を整えることは、心を整えること。
ママが落ち着くと、家の空気もやわらぐ。」
5. 「ありがとう」を増やすと、家庭がやわらかくなる
子どもが小さかった頃、私は「ありがとう」を口にする余裕がありませんでした。
毎日がバタバタで、やることに追われ、「早くして!」「なんでできないの!」とつい強い口調になってしまって…。
夜、寝顔を見ながら「今日も笑顔で言えなかったな」と反省する日ばかりでした。
そんなある日、4歳の息子が夕食を運ぶお手伝いをしてくれたんです。
思わず「ありがとう」と言うと、彼がぱっと笑って、照れくさそうに「どういたしまして」って。
その笑顔を見て、胸の奥がじんわり温かくなりました。
その日から、意識して「ありがとう」を増やすようにしました。
「手伝ってくれてありがとう」「食べてくれてありがとう」「ママのこと呼んでくれてありがとう」。
言葉を重ねるたびに、家の空気が少しずつやわらいでいくのを感じました。
不思議ですよね。
感謝の言葉って、相手だけじゃなく、自分の心までやさしくしてくれるんです。
「ありがとう」は、家の中に小さな灯りをともす言葉。
その灯りが、家族の心を照らしていく。
6. 比べない子育て|他の家庭と違っていい
正直に言うと、私はずっと“比べる育児”をしていました。
SNSで見る手作りお弁当や、笑顔の家族写真。
「うちの子は全然言うことを聞かない」「私はあんなに余裕がない」と、画面の向こうの誰かと自分を比べては落ち込んでいました。
そんなある日、娘と公園で遊んでいると、砂場で泥だらけになって笑う彼女の顔を見て、ふっと思ったんです。
「この子の幸せは、“うちの形”の中にちゃんとあるんだ」って。
他の家庭と違ってもいい。
手作りじゃなくても、外で買ったお弁当を一緒に食べて笑えるなら、それで十分。
その瞬間から、私は「比べること」より「味わうこと」に意識を向けるようになりました。
比べるたびに苦しくなるのは、自分を大切にできていないサイン。
だから今は、誰かと比べる代わりに、昨日の自分に「よくやってるよ」って声をかけています。
「比べなくていい。あなたの子育ては、あなたの家族にしかできない形でちゃんと光ってる。」
7. 子どもを信じる力を育てる|“見守る勇気”を持つ
「危ないよ」「やめて」「違うでしょ!」──そんな言葉が、いつも口から出てしまっていました。
子どもを思えばこそ、つい先回りして守ってあげたくなるんですよね。
私もまさにそうで、特に長男が幼稚園に入ったばかりの頃は、何か失敗しそうになるたびに口を出していました。
でもある日、園の帰り道で息子が小さな声で言ったんです。
「ママ、ぼく、じぶんでやってみたかったのに…」
その一言にハッとしました。
私の“手助け”は、この子の「やってみたい」を奪っていたのかもしれない、と。
それから私は、「見守る」ことを意識するようになりました。
失敗してもすぐに手を出さず、「どうしたらいいと思う?」と聞くようにしたんです。
すると、息子は考える顔を見せるようになり、少しずつ自分で工夫する力が育っていきました。
見守るって、放っておくことじゃない。
信じて待つこと。
その静かな時間の中で、子どもも、親もゆっくり成長していくのだと思います。
「子どもを信じる力は、親が“手を離す勇気”を持った瞬間に育ち始める。」
8. 「助けて」を言える親になる|頑張りすぎない勇気
「大丈夫、私ひとりでなんとかするから。」
そう言いながら、本当は全然大丈夫じゃなかった。
子どもが小さい頃、夫の帰りも遅く、毎晩ワンオペ。
泣き止まない赤ちゃんを抱きながら、自分まで泣いてしまった夜が何度もありました。
ある日、近所のママ友が私の顔を見て「さくらちゃん、顔色やばいよ」と心配してくれました。
その瞬間、涙が止まらなくなって、「実はもう限界で…」と初めて本音をこぼしました。
すると彼女は何も言わず、温かいお茶を淹れてくれたんです。
たったそれだけで、心がふっと軽くなりました。
それから私は、「助けて」と言うことを少しずつ覚えました。
実家やママ友、保育園の先生、行政のサポート…頼れるところはたくさんあったのに、
“迷惑をかけちゃいけない”と思い込んでいたのは自分だったんです。
誰かに助けてもらうことは、弱さじゃなくて勇気。
あなたが笑顔でいられることこそ、子どもにとっていちばんの安心です。
「“助けて”は、心を守る魔法の言葉。
頑張りすぎないあなたで、大丈夫。」
9. 日常に“楽しい仕掛け”をつくる|笑いと遊びが育児を変える
毎日が同じことの繰り返しで、「なんだか笑顔が減ってきたな」と感じた時期がありました。
朝の支度も、食事も、お風呂も、全部“やらなきゃいけないこと”になっていて。
そんなある日、ふと「ちょっと遊びを入れてみよう」と思ったんです。
たとえば、朝の支度のときは“だれが早く靴下を履けるかレース”。
お風呂のときは、“あわあわアイス屋さんごっこ”。
食後には、“ママが変顔で絵本を読む時間”。
たったそれだけで、子どもたちの目がキラキラして、私の心までほぐれていきました。
「遊び」って、特別なものじゃなくていいんです。
日常にちょっとした“クスッ”を足すだけで、空気がふんわり変わります。
笑い合う時間があると、叱る時間が減って、子どもとの関係も不思議とやさしくなっていきます。
完璧じゃなくていい。うまくいかない日こそ、ちょっとだけ遊び心を。
笑いは、育児の一番の栄養です。
「笑顔のある家庭には、“正しさ”より“楽しさ”が似合う。」
10. 今日の自分をほめて終わる|「よくやってるよ」と言える夜に
子どもたちが眠ったあと、リビングの静けさの中で、私はよく小さくため息をついていました。
「今日も怒っちゃったな」「ちゃんと向き合えなかったな」って。
寝顔を見ながら、自分の不器用さに涙が出そうになる夜もありました。
でもある晩、息子が寝ぼけながらつぶやいたんです。
「ママ、ぎゅーしてくれて、ありがとう。」
その一言で、胸の奥がふっとあたたかくなりました。
ああ、この子は“私の完璧さ”なんて求めていない。
“今日も一緒に過ごせたこと”をちゃんと感じてくれているんだ──そう気づいた瞬間でした。
それから私は、夜の習慣を変えました。
「できなかったこと」を数える代わりに、「今日できたこと」を一つ思い出す。
「朝ちゃんと笑顔で“おはよう”が言えた」「子どもを抱きしめた」──それで十分です。
どんな日も、あなたはよくやっています。
完璧じゃなくていい。泣いてもいい。怒っても、弱音を吐いてもいい。
だってそれだけ、真剣に子どもと向き合っている証拠だから。
「今日の自分をほめて眠る夜が、明日の笑顔をつくっていく。」
まとめ|完璧じゃなくていい、“笑顔でいる時間”を少しずつ増やそう
子育ては「うまくやること」より、「心を守ること」が大切です。
イライラする日があっても、泣きたい夜があっても大丈夫。
あなたが笑おうとするその姿が、子どもにとって最高の安心です。
少しずつ、少しずつでいい。
今日できたことを大切に、明日へとつないでいきましょう。
“あなたの笑顔が、子どもの未来を照らしています。”
参考・出典
※本記事は筆者の保育士経験と心理学的視点をもとに構成しています。個々の家庭状況により感じ方は異なりますので、ご自身に合う形でご活用ください。

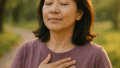
コメント